就活は「やり方」よりも「あり方」②1959年の日本理科学工業
2015年に法政大学大学院坂本光司ゼミに社会人として入学しました。 多くの企業を先生と一緒に視察に行き、この会社が最も印象に残っています。
日本理科学工業。
1959年、養護学校の先生が東京都大田区の日本理科学工業に就職の依頼にきました。 後に社長となる大山泰弘さんは、中小企業に余裕が無いとして、2回断られています。
「採用が無理だとわかりました。せめて働く体験だけさせてもらえませんか?」 頭を地面にこすりつけそうな先生の姿に心を打たれ、1週間の就業体験に承知しました。
二人の中学生は、朝8時の集合に対し、毎朝7時に会社の玄関まで来て待っています。 従業員は、そんな二人を、就活の為の自己アピールだとして批判しました。
二人は、昼休みも、中休みも、ラベル貼りの仕事に没頭して、休もうとしません。 従業員には、これも就職試験であるゆえの自己アピールとして不快でいました。
ただ、一生懸命に働いている顔が日増しに幸せそうなのは、嘘ではなさそうです。
一週間が経ちこれで関係を終わらせられると、ホッとしていた大山さんに従業員が言います。 「彼女たちを正規社員として採用してください。不都合な点は私達全員でカバーします」 近くで見守った従業員は、障がい者の素直で一生懸命な態度に、感動していたのです。
ミスをしたときに、「もう施設に帰りなさい」というと、泣きながら嫌がります。 大山さんには理解できませんでした。 障がい者として、仕事することなく安心な家庭でのんびりと暮らしすことこそ幸福なのに。
なぜ、怒られることや我慢することが多い就労をする必要があるのか?
禅寺のお坊さんは、こんな風に説きました。 「幸福とは、①人に愛され、②人に褒められ、③人の役に立ち、④人に必要とされること 人に褒められ、人の役に立ち、人に必要とされるには、働くことでしか得られません。 真の幸福とは働くことなのです。」
「ありがとう」と施設で言う障がい者が、働くことで「ありがとう」と言われる感動体験を得る。
今も日本理科学工業は、障がい者雇用70%以上を持続しています。 (人を大切にする経営学会:根本幸治)
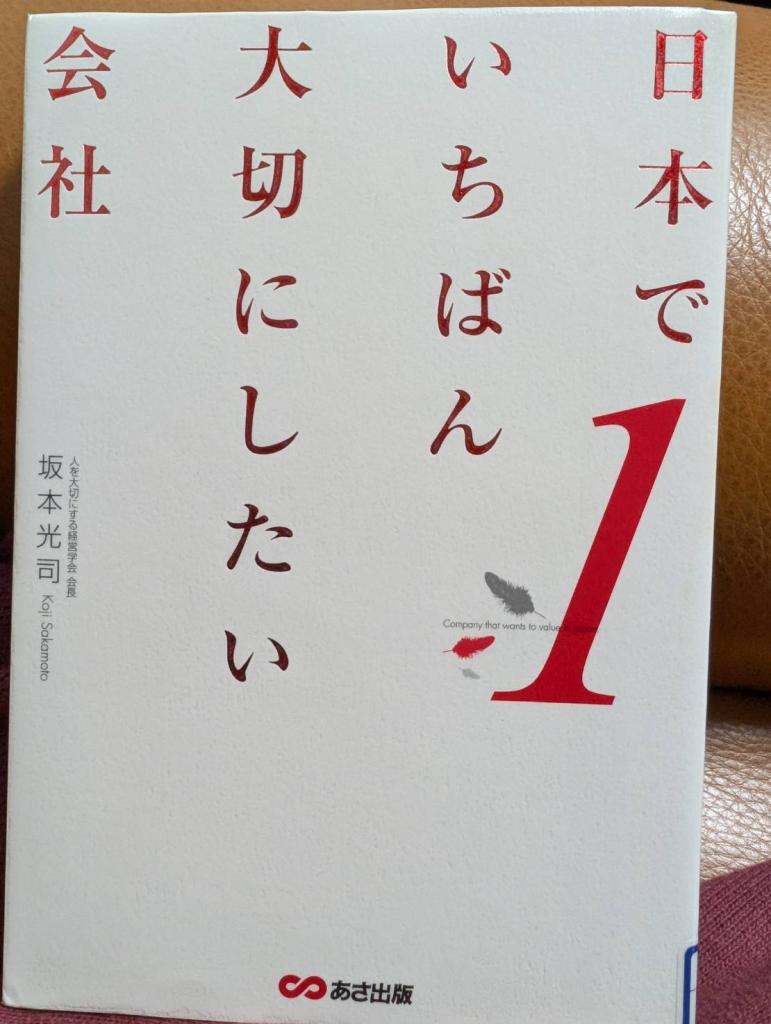

コメントを残す