商いは人を変えることができる
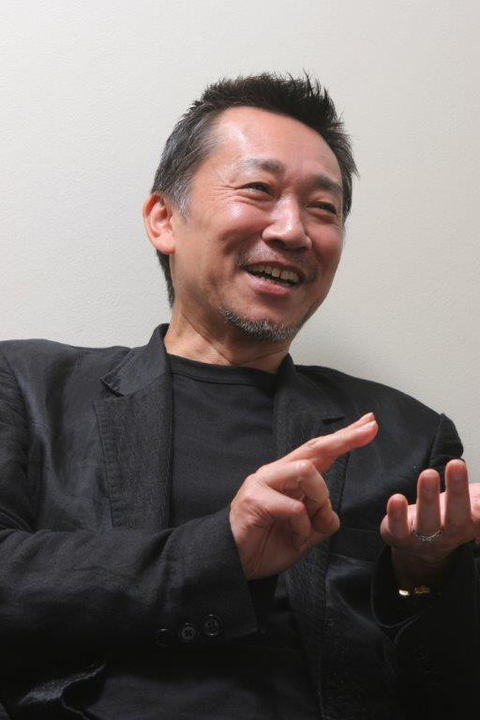





「商業界」笹井編集長のブログより。
商いは人を変えることができる
2017年04月02日(日) 06時00分00秒NEW !
テーマ:本日開店
お客は、価格やニーズといった合理的判断のみで商品を選んでいるわけではありません。
ときに感情への働きかけが選択を左右します。
そこには、自分の人生を豊かに彩ってくれる物語を求める気持ちが大きく影響しているのではないでしょうか。
東京・青山の万年筆専門店「書斎館」に、そんな物語を見ました。
モノに備わる人の心を
変えるストーリーを演出
約25年前の赤堀さんの毎日は、分刻みのスケジュールで詰まっていました。
そんな折、格別時計に興味があったわけではありませんが、アンティークの時計を買うことがありました。
分刻みの生活に合わせて電車に乗るのが習慣でしたが、買ったばかりのアンティーク時計は正確な時間を示さず、いつもの電車に乗り遅れることがあったそうです。
たった1本の電車を逃したことに怒り心頭に発しましたが、そのときふと目に飛び込んだのが、駅の外に広がる景色でした。
質屋の看板、ベランダで洗濯物を干す人、見上げた空の青――。
毎日通いながら、一度も景色を見たことがない景色でした。
そんな自分に驚き、こう思ったそうです。
「時間に追われる余裕のない暮らしは、いったい何だろうか」
加えて、アンティーク時計というモノが人生観を改めさせてくれるきっかけとなったことに気づきました。
モノは人を変えることができる、と。
そこで家業で親しんできた文房具の世界で、自分が味わったような転回の物語を紡ぎ出してくれるようなアイテムは探し、行き着いたのが万年筆だったのです。
だが、万年筆は筆記具としての役割をボールペン、さらに言えばITに取って代わられ、終えていた存在。
市場規模はピーク時の1000分の1にまで減少しています。
存在しないニーズをつくるにはどうすればいいか――そこで思いついたのが潜在意識への働きかけでした。
「ソニーのウォークマンがそうであったように、発売されると『そうそう、こういうのが欲しかった』と人はいうけれど、形になるまで、誰もそんなことは思っていなかったはず」
万年筆の機能は必要とされていません。
しかし、万年筆によって演出される時間や空間も用途だと説明したとき、見え方は変わり、「こういうのが欲しかった」という必須アイテムになりえます。
その上で欠かせないのは、「インクを入れる時間や汚れた手を洗うという不便さを楽しむ」というストーリーテラーでした。
それを言葉ではなく、店が語り、お客が体感する必要がありました。
赤堀さんが思い浮かんだのは、“本能”というキーワードでした。
「売れていないとは、コアターゲットがいないということ。老若男女を対象にするなら、人間の動物としての本能に訴えるしかない」
書斎館の照明が暗いのは、人間工学の見地から人が最も安心感を覚える照度にしているから。
そして、バックヤードも含め、店内に90度の角を73カ所もつくっているのは、動物的な本性は隅に寄ることで安心を覚えるから。
加えて、アンティーク文具をそろえることで、誰にも共通する“幼い頃の思い出”を刺激するのです。
つまり、安心と安全さを感じる環境の中、工芸品のような高級万年筆から普段遣いまで、7カ国2000本を数える製品と向き合ったとき、顧客は機能やニーズという既成の価値観を離れたところで万年筆と出合うことができると。
世界を変える
万年筆の力を信じて
お客は入り口から店内へと足を運ぶ中で推移する“物語”に心動かす経験をします。
そのための接客であり、新しい価値観の醸成を含んだ商売なのです。
だから定価販売が原則、値引きは行っていません。
動線から外れたロケーションと内容を把握できない店構え、しかも扱う商品が定価販売の万年筆。
「1年でつぶれる」とコンサルタントの言うように無謀な賭けであったのかもしれません。
しかし、蓋を開ければ2001年の開店以来、好調な売上げ続けています。
訴求力がないと言われた万年筆でありながら、足を運ぶ客の半数は20代であり、客単価は約3万円。
リピーターも多いといいます。
出店依頼は引きも切りません。
しかし、赤堀さんはすべて断っているそうです。
「店を増やすことに関心がない。本当に大きいことはいいことなのかという疑問があります。目の届く範囲でやりたい。続けることがいちばん難しいのだから」
事業の拡大よりも関心を払っているのが“感動”という思です。
「朝からみんな忙しそうにしていますが、インクを入れる面倒、万年筆という道具の止めてくれる時間を楽しめるなら、世の中変わると思います」
モノを通じ、ものの見方を変えるという経験と、それに伴う感動をいかに提供できるか――。
価格競争や新奇さに左右されない物語発信型のビジネスモデルが書斎館に見て取れます。
閉じた店が
ニーズのない万年筆を魅惑的にする
高級ブティックや古美術店が並ぶ骨董通りから奥に一つ入った、閑静というにはあまりに人気のない路地に「書斎館」はあります。
砥草と敷き詰められた白い石、百日紅を配した前庭から店内へと、自然と足を導くよう石段は刻まれているものの、屋内のほの暗い照明と、京都の町家を思わせる長細いエントランスに目を移した途端、それ以上奥へと進むことに少し戸惑う店づくりです。
説明がなければ、ここが万年筆とアンティーク文房具を販売する店だとは分からないでしょう。
実際、近隣のショップや住民の中には、開店から数年間、何の店なのか知らない人もいたといいます。
青山に展開する多くの店の特徴は、「開いて閉じる」店づくりにあります。
つまり総ガラス張りで、外から商品や店の様子が一目瞭然で、開かれた印象によって店へと誘導していきます。
対照的に書斎館は「閉じて閉じる」ところが特色といえるでしょう。
「ニーズを満たすだけでは感動を呼ばない」
書斎館を運営する久菱成文堂の赤堀正敏さんは言います。
ニーズを満たすことが感動につながらないのは、顧客の抱いている予測を超えないからです。
では、予測を外せば感動をもたらすのでしょうか。
意外性を狙うと、いっときの流行にはなったとしても、奇を衒うことになり、息の長い商売にはなりえない、と赤堀さんは言います。
しかも、ただでさえ手書きの習慣が薄れつつある時下、インクを入れるにも手間のかかる万年筆には、ニーズがほとんど存在しません。
そこでは意外性という物語の演出は効力を発揮しません。
「一等地のデパートでさえ文具の売上げが減少する中、万年筆には市場もなければ需要もない」
そう赤堀さんがいうように、出店にあたって依頼したコンサルタントのレポートにはネガティブな要素しかなく、ビジネスではなく「賭け事」とさえ言われました。
周囲は誰一人賛同しなかった創業でしたが、赤堀さんは勝算を感じていたそうです。
そこには赤堀さんのライフヒストリーが重なっていました。

コメントを残す